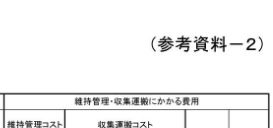大学に進学すると、急に耳にする単語があります。
「レジュメ」
大学の講義やゼミなどで配られる資料を、こう呼ぶことが多いですよね。
でも、高校までは「プリント」って言っていました。
なぜ大学ではレジュメと呼ぶのでしょうか?
疑問に思ったあなたは、きっと優秀で鋭い感性の持ち主なのでしょう。
その疑問に答えるために、色々と調査しました。
調査結果をお話します。
プリントとレジュメの違い
まず、簡単に言葉の定義から見ていきましょう。
・プリント:印刷物全般
・レジュメ:論文やプレゼン内容の要約資料or履歴書
レジュメはフランス語の要旨・要約資料を指します。
英語圏では、履歴書という意味で使われることが多いです。

本来の言葉の意味から考えると、レジュメはかなり使い所が限定されるはずですね。
でも、大学に行くと紙の資料全般がレジュメと呼ばれています。
これには、こんな理由があったのです。
大学教授が原因だった

大学生たちがレジュメという言葉を使うきっかけは教授です。
講義中、こんなセリフを聞いたことはありませんか?
「入り口前にレジュメを3種類置いています。各自取ってください」
「みんなレジュメはありますか?足りない人!」
「レジュメのグラフを見てください…」
教授がこんな風に使っているんですよね。
教授が使うから、学生たちも自然と使うようになるわけです。
ではなぜ教授はレジュメという言葉を好んで使うのでしょうか?
答えは簡単。
教授たちが「研究者」だからです。
講義を行う教授たちは、それぞれ専門分野を持っています。
研究成果を論文にまとめたり、学会などでプレゼンする機会がたくさんあります。

自分の研究成果を発表する際、毎回全員に論文を印刷して配るわけにはいかないですよね。
荷物になるし、時間も限られています。
そこで必ず作るのがレジュメです。
本来の意味での「研究成果を要約した資料」を作成し、配布するわけです。
教授たちにとっては、学生向けの講義もプレゼンの一種。
自分の専門分野について、要点をまとめて伝えてる場という意味では同じなのです。
小学校、中学校、高校の先生とは授業に対する意識が全く違います。

高校までの先生が作るものは、授業に理解度を高めるための「プリント」。
大学教授が講義で配るのは、研究成果の要旨を切り取った「レジュメ」。
このような意識や立場の違いから、大学教授たちは自然とレジュメという言葉を多用します。
社会人がレジュメと言わない2つの理由

大学生活中は毎日のように聞いていたレジュメという言葉。
社会人になると、ほとんど使わないというのはご存知でしょうか?
これには、2つの理由があります。
・中卒、高卒には聞き慣れない言葉
・履歴書との混同を避けるため
社会人の学歴は様々です。
中卒の人もいれば、大卒の人もいます。
役員クラスの人でも中卒や高卒の人は大勢います。
聞き慣れていない人にとっては、レジュメという言葉は違和感が残ります。

さらに、英語圏ではレジュメという言葉は「履歴書」「職務経歴書」を意味します。
企業の公文書が英語の場合もあるし、英語圏の企業と取引しているところもたくさんありますよね。
どちらの意味で言っているのか、分かりにくいことがあるんです。

意味を混同しやすい言葉を、あえて使う必要はありません。
社会人は何と呼ぶの?
では、社会人は何と呼ぶのでしょうか?
多くの場合は、単に資料と呼びます。
会議資料、プレゼン資料などと呼ぶのが一般的です。
ビジネスの現場で何か紙を配る時には、紙の左上や右上に資料番号を記入します。
「資料1」「参考資料1」などですね。
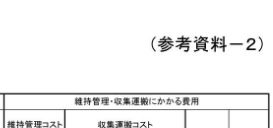
ビジネスの現場では、多くの事柄を話し合います。
単に「レジュメを見てください」と言っても「どれだよ?」と思われてしまうのです。
「資料1をご覧ください」と言えば、明確です。

このように、単に「レジュメ」と呼ぶ機会はほとんどありません。
大卒の人しかいない企業だったとしても、自然とレジュメという言葉を使わなくなっていきます。
レジュメというと相手が不快になる!?
レジュメという言葉。
何気なく使っていると思いますが、不快な思いをしている人がいることはご存知でしょうか?
私が町内会100人にアンケートした結果、10人に1人は「不快だ」と言っていました。
ちょっと偏った調査ですが(笑)
「なんで資料って言わないの?」
「なんか、鼻につく」
こんな印象を持つ人もいるのです。
レジュメに限った話ではありませんが、カタカナ語を使いすぎると相手を不快にさせることがあります。

人間は、会話中人聞き慣れていない言葉の割合が増えると不快に感じるもの。
あなたは大丈夫でしょうか?
最近では「コンプライアンス」「アジェンダ」「コンセンサス」など、カタカナ語を使う人が増えました。
使うのは自由ですが、相手に伝わっているでしょうか?
自分が話す言葉が本当に相手に伝わっているか。
これを見抜くのも、就活でよく求められる「コミュニケーション能力」の一つです。
カタカナ語を使うのが悪いのではありません。
相手がどう感じているのか察することができないのが問題ということですね。
大学生活は順調ですか?
いかがでしょうか。
大学生活以外ではレジュメという言葉はあまり使われません。
そのことだけ、頭の片隅に置いていただければ幸いです。
ところで、あなたはファッションセンスに自信がありますか?
この前、女子大生と話をしていた中で「男子のファッションはダサい人が多すぎ」という話題が出ました。
ギクッとした人。
詳細は「男子大学生の服は何着必要か」をご覧ください。